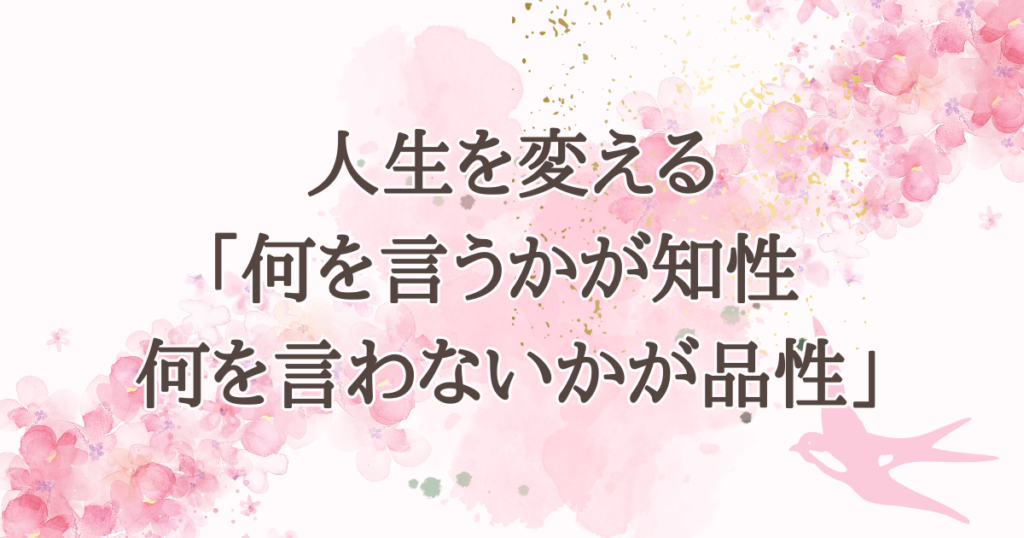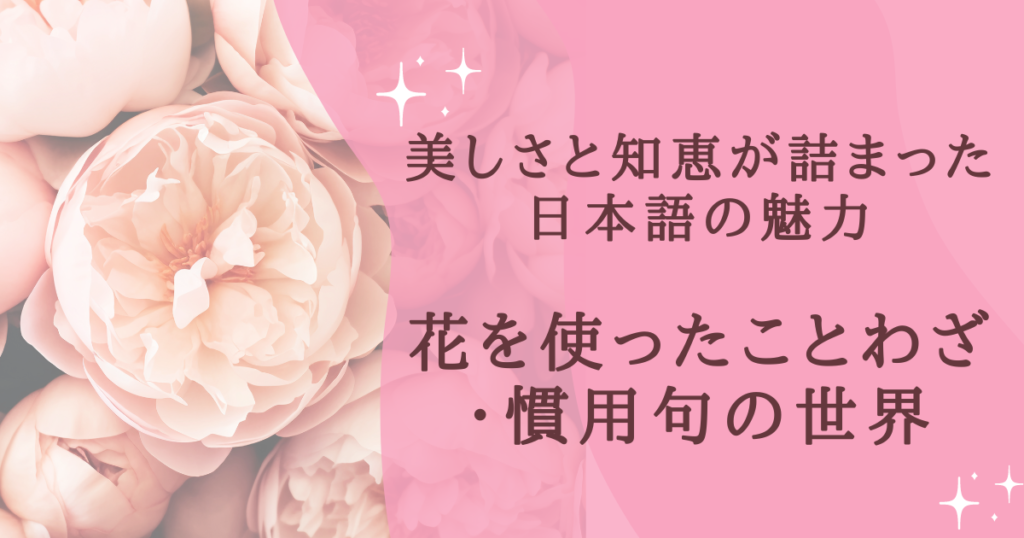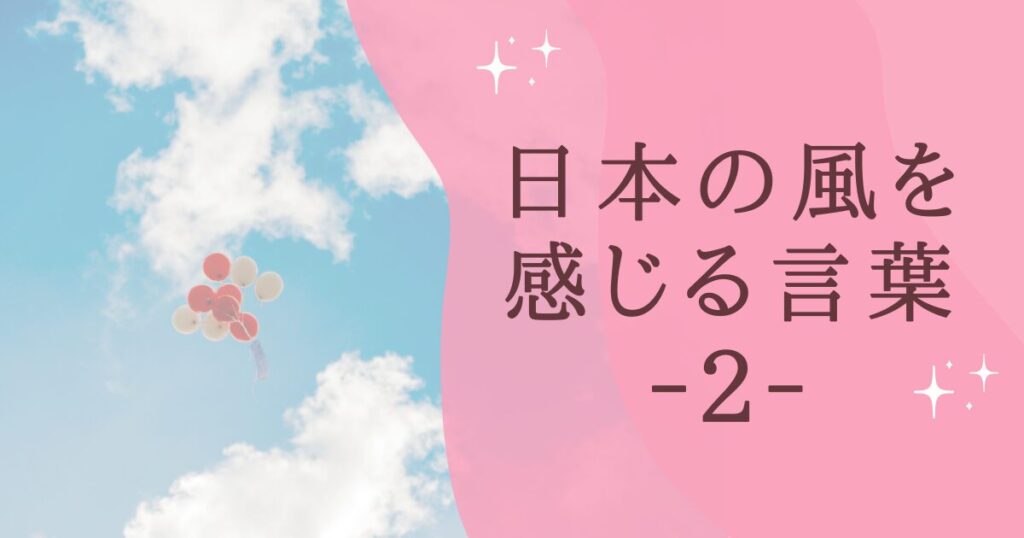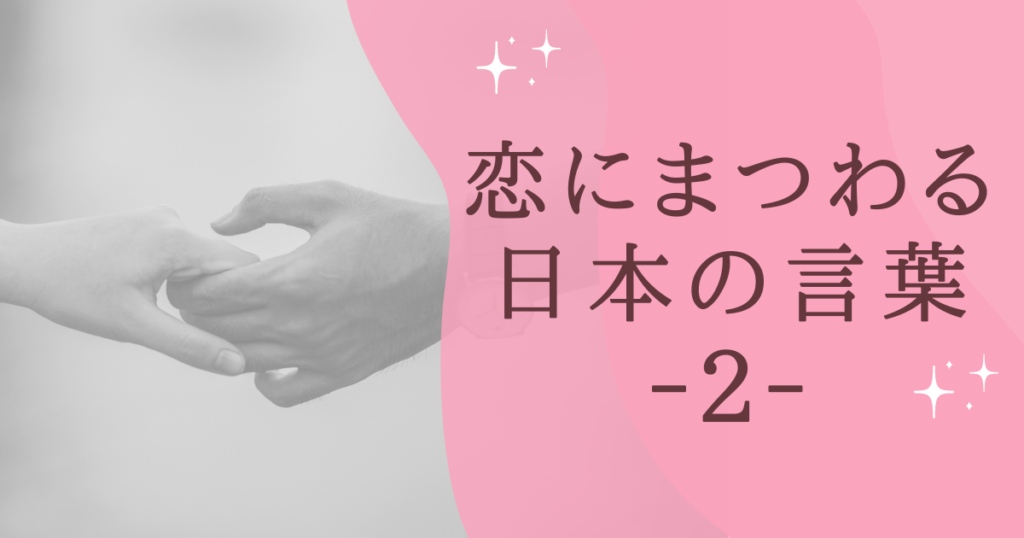日本の言葉– category –
大和言葉をはじめとする日本の言葉を紹介した記事を集めています。
-

人生を変える「何を言うかが知性 何を言わないかが品性」
「何を言うかが知性 何を言わないかが品性」 「何を言うかが知性、何を言わないかが品性」という言葉は、小沢一敬さんというお笑いタレント・YouTuber・俳優がお話された中の言葉です。言葉を選ぶ力がその人の知性を示し、黙る勇気や言葉を控えることがその人の品性を表すという意味を持っています。人間関係や日常生活、ビジネスの場でもこの言葉が示唆する重要なメッセージは深いものです。本記事では、この言葉の意味と背景を掘り下げ、現代においてどのように応用できるかを考察していきます。 「何を言うかが... -

『しにくい』と『しづらい』の違いって?微妙な日本語のニュアンスを徹底解説!
「しにくい」と「しづらい」は違うの? ―言葉の微妙なニュアンスを徹底解説! 「しにくい」と「しづらい」って何が違うの? 日本語には、同じように見えるけれど、実際には微妙にニュアンスや使い方が異なる表現がいくつかあります。たとえば「しにくい」と「しづらい」。この二つは日常会話やビジネスシーンでもよく使われますが、「何となく似ているけど違うような気もする…」と感じたことはありませんか? この疑問に対して、具体的な違いを説明しながら、どのように使い分けるとよいかについて詳しく掘り下げ... -

恋にまつわる日本の言葉‐1‐
恋愛に関する日本語には、風情豊かな大和言葉が数多く存在します。その中でも特に、待宵、恋蛍、逢瀬という言葉は、古来から愛の情景を詠んだ歌や物語にしばしば登場し、深い感動を呼び起こします。この記事では、それぞれの言葉の意味とその背景について探求し、日本文化における恋愛の美学を探っていきます。 【寂しげな美しさ「待宵(まつよい)」】 待宵とは、「夜が明けるまで待ち続けること」という意味を持ちます。恋の待ち人を待ち続ける情景を描写する際に使われることが多く、その中には深い切なさと希... -

時をあらわす日本の言葉-4-
大和言葉に秘められた夜の情景 大和言葉には、自然や季節、日常の瞬間を繊細に表現する言葉が数多くあります。これらの言葉は単なる語彙の域を超え、日本人の感性や風景に対する美意識を映し出すものとして現代にも深く息づいています。特に夜に関する言葉は、その時間帯の情景や心情を豊かに描写するもので、詩や文学の中でもしばしば登場します。今回は、そんな夜に関連する大和言葉の中でも、「小夜(さよ)」「暮夜(ぼや)」「暗夜(やみよ)」「短夜(みじかよ)」「朧月夜(おぼろづきよ)」について、その... -

美しさと知恵が詰まった日本語の魅力― 花を使ったことわざ ・慣用句の世界
花を使ったことわざ・慣用句に学ぶ日本の美意識 花は日本文化において、美しさや儚さ、生命力を象徴するものとして古くから優しく大切にされています。多くのことわざや慣用句に登場します。 今回は、花に関する3つの日本語のことわざや慣用について、それぞれの意味や背景、日常生活での活用例を詳しく解説します。 【「いずれ菖蒲(あやめ)か杜若(かきつばた)」】 意味 「いずれ菖蒲(あやめ)か杜若(かきつばた)」は、どちらも美しくて優れており、選びたい様子を表すことわざです。このことわざは、どち... -

日本の風を感じる言葉‐2‐
大和言葉はそれぞれ自然の美しさや、人間の感情を繊細に表現することができる言葉です。これらの言葉を通じて、日本の四季や風景、人々の心情が詩的に描かれ、人の心に深い印象を残します。 こちらでは風にまつわる言葉をご紹介します。 【「青嵐(あおあらし)」―自然の力と青春の象徴】 青嵐という言葉は、日本語特有の美しい表現であり、自然の力強さと風の澄んだ爽やかさを同時に感じさせます。青嵐とは、草木が揺れ動き、空が広がる様子を表現する言葉であり、詩的なイメージを喚起します。自然の中で感じる... -

浮かぶ雲と日本の言葉‐1‐
自然と人々の心を映す古語の世界 日本語の古典文学や詩歌の中には、自然を表現する美しい言葉が多く存在しています。その中でも、「天霧る(あまぎる)」「雲居(くもい)」「片雲(へんうん)」といった言葉は、雲や霧、天候に関連し、自然と人々の心情を見事に映し出しています。本記事では、これらの言葉が持つ意味や背景、そして古典文学の中でどのように使われてきたかについて考察していきます。 【「天霧る(あまぎる)」―曖昧さと不安定さを映す自然現象】 「天霧る(あまぎる)」は、霧や雲が空を覆い、... -

恋にまつわる日本の言葉‐2‐
恋愛にまつわる言葉には、時代や文化を反映する深い意味が込められています。特に日本語には、その繊細で詩的な表現が豊富に存在します。ここでは、日本語の大和言葉「片恋」、「心恋し」、「恋の端」に焦点を当て、それぞれの意味とその背景、そして現代における意義について探ってみたいと思います。 【「片恋(かたこい)」―苦しみや切なさを】 「片恋」という言葉は、一方通行の恋、片思いを指します。その一方的な想いが、しばしば切なく、深い感情の波として表現されます。この言葉は、古来から日本文学にお... -

きらめく星々と日本の言葉‐1‐
日本の自然や文化には、星にまつわる美しい言葉が数多く存在します。特に大和言葉は、その響きや意味に深い感情を込めて表現されています。本記事では、三つ星、明星、暁星の三つの言葉に焦点を当て、それぞれの意味や使用される背景を詳しく探求します。これらの言葉は、ただの星を指すだけでなく、日本人の心の奥に息づく情緒や文化的な価値観をも映し出しています。 【三つ星(みつぼし)】 「三つ星」は、その名の通り三つの星を指しますが、特に夜空に浮かぶ星々の中でも特に目立つものを指すことが多いです... -

花々にまつわる日本の言葉‐4‐
美しき花にまつわる表現―「咲き初める」「咲き誇る」「咲き乱れる」「咲き渡る」 日本語には、自然を繊細に表現する言葉が数多く存在します。特に「大和言葉」と呼ばれる古くから使われてきた日本の伝統的な言葉は、情景や感情を豊かに描き出す力を持っています。今回は、花が咲く様子を描写する4つの美しい言葉「咲き初める(さきそめる)」「咲き誇る(さきほこる)」「咲き乱れる(さきみだれる)」「咲き渡る(さきわたる)」に焦点を当て、それぞれの意味や使い方について詳しく見ていきます。これらの言葉を...